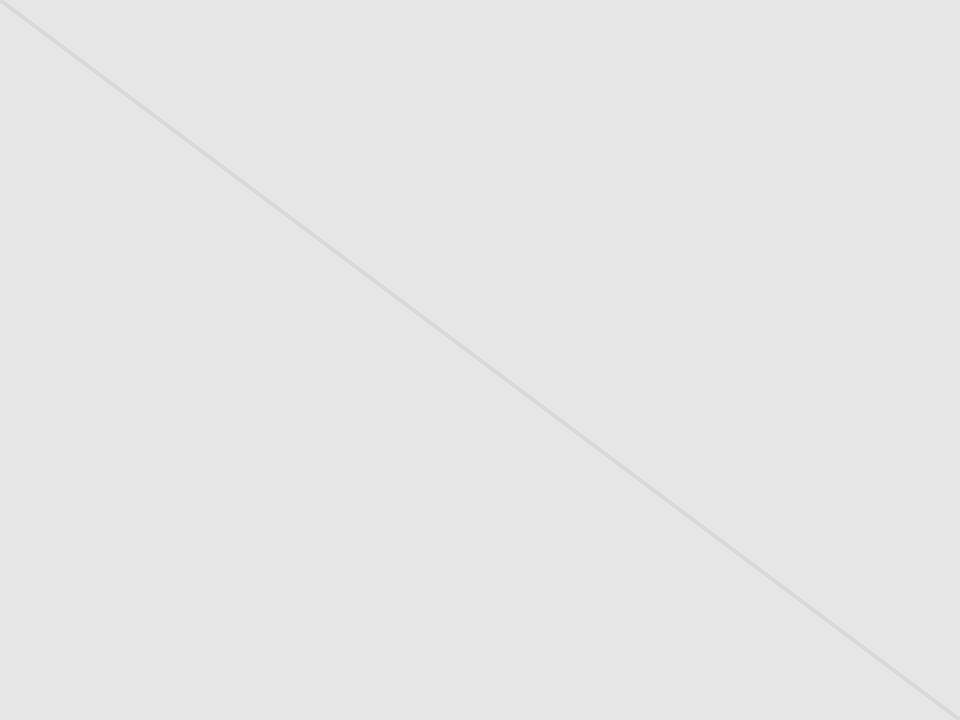脳と幸せの仕組み
Feb 3, 2023
このページは現在執筆中です。脳の中で神経伝達物質がどのように精神機能に影響を与え人間が幸せを認知するのかについて書きますが、その説明の正確性、そもそものこのページの必要性について議論しているところです。内容の正確性は保証しませんし、不完全であるため Now からの主張であるとは扱いません。それらをご理解いただけた方はお読みください。
————
友達の重要性 では幸せというのは脳内の神経伝達物質であるセロトニン、オキシトシン、ドーパミンによる影響だと書いた。このページではもう少し詳細に脳と幸せの仕組みについて書いていく。このページでは脳の神経伝達物質について書いてあるが、Now のチーム内には科学者がいないため説明に間違いが入っている可能性がある。幸せとは何かを考える上で脳の仕組みから考える方が、説明しやすく、また友達の重要性についてみんなが考えやすくなるのではという意図でそのような話をしているので、この文章内で間違いがあれば是非ご指摘いただきたい。では、脳と幸せの仕組みについて考えていく。
神経伝達物質はそれぞれこういう役割です
おそらく脳は進化の過程でこのように進化したから神経伝達物質はこうできてるんでしょうね
なので幸せはこういう仕組みです
だから友達の重要性に書いてある通り幸せに友達は重要だと思います
神経伝達物質の役割
セロトニン: 自律神経の調整を通して心身を整える
メラトニン: セロトニンから生成され、睡眠と覚醒を調節する
オキシトシン: 安心や愛を感じさせる、ストレス値をさげる
過度なストレスはノルアドレナリンやドーパミンなどの神経伝達物質を放出し、これらの濃度が前頭前野で高まると、神経細胞間の活動が弱まり、やがて止まる。ネットワークの活動が弱まると、行動を調節する能力も低下します。視床下部から下垂体に指令が届き、副腎がストレスホルモンであるコルチゾールを血液中に放出して、これが脳に届くと事態はさらに悪化する。ノルアドレナリンとコルチゾールの濃度が高まると、危険に備えるよう他の神経系に警告を発したり、恐怖などの情動に関わる記憶を強めたりする。これによって意欲を感じにくくなり、ドーパミンの分泌を抑制するから、やはりストレスを緩和するというオキシトシンがもつ影響は大きい気がするな。
ドーパミン: 意欲や成功によって得られる報酬を感じさせる
ノルアドレナリン: ドーパミンの代謝産物として生まれ、集中力を高めたり臨戦体制をつくる
この他にも合計約20種類ほどの神経伝達物質が確認されているが、主に感情システムに直接的に影響を与えていると思われるものをピックアップした
間違ってたら教えてね
進化の結果
脳の仕組みは進化の結果だと考えている
そう考える理由は幸せと認知するセンサーの仕組みを考える上で必要だから
この考えを押し付ける意図はないので読み飛ばしても構わない
はじめる
人間含め生物は生存と生殖と子育てを目的に活動している
自然の中でその目的に合うように感情システムは形を成してきた
セロトニン: 自然界で生存・生殖という目的を果たすには、エネルギー効率を最適化する必要があり、そこでドーパミン分泌をコントロールする機能が必要だったため作られるようになったのではないか
メラトニン: これもエネルギー効率の最適化機能
オキシトシン: 人間は社会的動物として群れで生活する。それが生存確率が高かったから。群れで資源獲得と資源分配をするには、信頼や協力や贈与などが必要。それを感じる報酬の機能として生まれたのではないか。また、仲間との関係がうまくいっている場合、資源獲得も資源配分もうまくいき、生存と生殖と子育てにおけるリスクは減るため、その低リスクな状況でエネルギーを無駄に消費しないために、ストレス値を下げる効果をもったのではないか。
ドーパミン: 資源獲得をしようという意欲をかきたて、その成果に対して報酬を与えるための機能として生まれた。目標に向かって取り組んでいる時、目標を達成した時、それを他者に讃えられた時、それらの瞬間がワクワクしたり、嬉しかったり、誇らしかったりするのはそれ。
幸せの仕組み
事実→認知の順番
幸せと認知する
認知する上でセンサーがある
センサーは生得的なものと習得的なものがある
それぞれのセンサーに合わせて幸せを認知する
生得的なものは進化の過程で重要だったものに基本的に反応する
それは上の進化の結果で書いたような内容
だから例えば信頼できる群れの仲間=友達・恋人・家族とのグルーミングでオキシトンはでる
グルーミングといえど具体的にどんな事実に対して幸せだと認知するかは習得的な差が出る
例えば幼少期に新しいことに挑戦することを親から認められなかった、つまり報酬を得られなかった人は、新しいことに挑戦することに対してドーパミンが出にくい。また、例えば親しい人間関係を築く経験が少なくこれまで必要性を強く感じてこなければオキシトシンが出にくかったり、そのような関係を求める意欲がなく、その方向にドーパミンが出ないとかがありそう。
友達の重要性
人間の脳と幸せとかの仕組みってだいたいこんな感じなんだろうな。で、そうするとやはりセロトニンとオキシトシンとドーパミンは幸せには必須。その中でもオキシトシンはドーパミンをうまく出す上でも重要な役割をもっているから、ここのオキシトシンを出すための友達という関係はすごく重要だと思う。